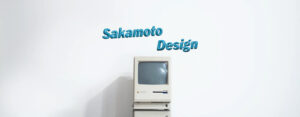Webサイトは現代のビジネスシーンにおいて必要不可欠な存在です。Webサイトを開設していれば営業の幅を広げやすくなります。
「SNSがあるから大丈夫」と一概には言えません。Webサイトの役割を理解した上で、どのようにウェブで活用をしていくか決めることが大切です。
この記事では、Webサイトの種類や目的、メリット・デメリットなど、Webサイトの基本をご紹介していきます。
Webサイトとは?
Webサイト(ウェブサイト)とは、インターネット上で公開されている複数のWebページの集合体です。
ユーザーに情報を伝えるため、買い物をしてもらうためなど、様々な目的で公開されています。
Webサイトの種類
Webサイトには様々な種類があります。ここでは代表的な種類を6つご紹介します。
| コーポレートサイト | 会社の情報・サービスを紹介し、信頼性を向上させる。 |
|---|---|
| ECサイト | 商品を販売するオンラインストア。 |
| ブログ・オウンドメディア | 強力な情報発信・SEO対策ツールになる。 個人ブログや企業が運営するオウンドメディアなどがある。 |
| ランディングページ(LP) | 特定の商品の販売や資料請求・申し込みの促進。 |
| 採用サイト | 求人情報を掲載し、人材を採用することに特化したページ。コーポレートサイトとは別に開設されることも多い。 |
| 会員制サイト・Webアプリ | ユーザーがログインして使うWebサービス。例としてNetflixなどの動画配信サイト、InstagramなどのSNSがあげられる。 |
Webサイトの目的

Webサイトの目的も様々です。ここでは特に重要視すべき4つの目的をご紹介します。
認知度向上
自社の存在を多くの人に知ってもらい、業界内での認知度を高めることが目的です。特に新規企業や新商品・サービスのローンチ時に重要になります。
売上・お問い合わせ獲得
商品・サービスの購入や問い合わせを増やし、売上向上を狙います。ECサイトやBtoB企業のサイトで特に重要です。
ブランドのイメージアップ
「信頼できる企業」「おしゃれなブランド」「社会貢献している企業」など良い印象 を持ってもらい、ブランド価値を向上させることが目的です。目指しているイメージを反映させましょう。
人材採用
求職者に企業の魅力を伝え、優秀な人材を獲得することを目的とします。特に競争の激しい業界では、採用サイトの作り込みが重要になります。
Webサイトのメリット・デメリット
メリット
集客の幅を広げることができる
Webサイトはインターネット上に公開されているため、時間や地域の制約を受けずに、多くの人に情報を届けることが可能 です。
強力な営業ツールになる
Webサイトは、自社の商品・サービスの魅力をいつでも伝えられる営業ツール になります。
信頼性が向上する
公式サイトとしての情報公開、実績紹介や採用情報の掲載で企業としての信頼性が向上します。
デメリット
開設・運営にコストがかかる
Webサイトを作る初期費用と、運営するためのサーバー費やドメイン費など維持費がかかります。
専門知識がいる
Webサイトを効果的に制作、運用するためにはプログラミングなどの専門的な知識が必要です。
人的リソースが必要
Webサイトを制作する人、運営する人、お問い合わせに対応する人など人的リソースも必要です。
WebサイトとSNSの違い

役割
Webサイトの役割は主に、詳しい情報の発信、ブランディングです。SNSの役割はコミュニケーション、リアルタイム発信です。
それなりの情報量を掲載し、ユーザーにしっかりと情報を伝えたいのであればWebサイトがおすすめです。その日の出来事やすぐに伝えたい情報を手軽に発信するのであればSNSがおすすめです。
WebサイトもSNSも運用し、両方の良さを活用しながら売上に繋げていくという運用が理想かもしれませんね。
スタイル
Webサイトは情報が蓄積されているストック型です。SNSは常に新しい情報が流れて来るフロー型です。
SNSにも投稿した過去の情報は蓄積されていますが、仕組み上常に新しい情報が流れてきます。また、新しい情報を見たいユーザーがメインのため、流れてきた情報が古いものであればユーザーエクスペリエンスが下がってしまう可能性もあります。
どのような情報をどのように伝えていきたいか、競合がどのような使い方をしているか、事前に調べて決めておくことがおすすめです。
アクセス
Webサイトは検索エンジンや宣伝などを通してユーザーが流入します。SNSの場合、シェアやいいねなどによって人から人へアクセスが拡散されていきます。
Webサイトの場合いわゆるSEO対策が大切で、セマンティックなコーディングや正しいキーワードの設定など、検索に引っかかりやすくする対策が求められます。
SNSの場合、ユーザーのホームに投稿が表示されることであったり人気のあるタグ設定が大切です。いいねやコメントなど、反応が多ければホームに表示されやすくなります。
Webサイトの制作方法

Webサイトの作り方は、コーディング、ローコード、ノーコードの3通りです。ここでは、各項目について詳しく解説していきます。
コーディング(プログラミングを一から行う)
Webサイトは、Webブラウザと呼ばれるアプリケーション上に表示されています。
ざっくりで言えば、Webブラウザが読み取ったプログラムをもとに画面上にサイトが表示されるという仕組みです。つまり、Webサイトを作るためにはWebサイトを構築するためのプログラミングが必要になります。
WebサイトはHTMLというプログラミング言語をベースに、そのほかCSSによる見た目の装飾や、Java Scriptによるアニメーションなどサイト制作に適した言語でコーディングを行うことによって構築されます。
コーディングが完了した後は、必要なファイルを契約したサーバーにアップロードし、ドメインと呼ばれるネット上の住所と結びつけることによりWebサイトを公開できます。
ローコード(最小限のプログラミングを行う)
ローコードとは、できるだけコーディングを行わずにWebサイトを作ることです。
CMSを使うことが多く、用意されたテンプレートを基本的には使用し、必要があればコーディングでデザインや動きを修正・追加していきます。一からコーディングを行うよりも手間を省くことはできますが、言語の知識は必要です。
無料で利用できるWordPressというCMSは有名ですが、その他にもマーケティング機能を持ったものやセキリュティに強いものなど様々な特徴を持ったCMSがあります。
また、CMSを利用することによって、ニュースやブログといった更新性の求められるコンテンツも手軽に作ることができます。
ノーコード(プログラミング不要のツールを使用する)
ノーコードとは、コーディングを一切使わずにWebサイトを制作することです。代表的なツールとしてWiXやSTUDIOがあります。
ノーコードの場合、テキストや画像などを感覚的に配置することができるため、より手軽にWebサイトを作ることができます。
プログラミング言語の知識がなくてもWebサイトを作ることが可能で、初心者の方にもおすすめです。しかし、コーディングよりもデザインや機能が制限されるため、理想とするWebサイトが実現できそうか事前に明らかにしておくとよいでしょう。
Webサイト制作は誰が行うの?

Webサイトを誰が作るかは、自分、自社の担当者・制作部署、Web制作会社、フリーランスの4パターンに分けることができます。
誰が指揮を取るか、誰が作るかということも重要です。
自分で作る
Webサイト制作の知識とスキルがあれば、自分で作るという方法を選択するのが良いと思います。
プログラミング不要のWebサイト制作サービスもあるため、デザインができれば簡単にサイトを作ることが可能です。
自分でWebサイトを作ることによってサイト制作のコストがほとんどかからず、自分のペースに合わせた自由な制作進行をすることができます。
自社の担当者・制作部署
Webサイト制作・運営の体制を自社で整えるとコミュニケーションもとりやすく、よりスムーズな制作・運営ができます。
もともと自社にWeb制作ができる社員が在籍していれば低コストで実現可能ですが、新規制作の場合、専任の社員を新規で募集すると思います。そうなると採用コストもかかりますね。
また、必ずしもWebサイト制作のスタートメンバーが会社に所属し続けるとは限りません。複数人で運営し、いつでも制作を引き継げるような体制がベストです。
Web制作会社
Web制作を専門で行なっている会社に委託するという制作方法もあります。自社で専任の部署を用意するよりも簡単にWebサイト制作をすることができます。
Web制作のプロが集まっており、トラブルがあった時にも素早い対応が期待できます。その分、それなりの人数が関わるため制作コストはかかります。
Webサイトは開設後の更新も重要なため、運営を代わりに行なってくれるサービスを提供している会社に委託するとさらに効果アップが見込めます。
フリーランス
最近はフリーランスの方が個人でWeb制作を行なっていることも珍しくありません。かくいう僕もフリーランスです。
ネットで仕事を依頼するクラウドソーシングを中心に活動を行なっている方もいますし、会社のようにリアル営業を行なっている方もいます。
フリーランスは基本的に個人で仕事を請け負うため、Web制作会社に頼むよりもコストを抑えることができます。
どこにコストがかかるの?
Webサイトの制作・運用にはコストがかかります。コストを抑えるために自分で制作をしたとしても、必要最低限のコストはかかります。
どこにどれだけコストがかかるかあらかじめ計算しておいて、費用対効果を見ながら運営をしていくことが重要です。
ここではコストがかかる5つの要素をお伝えします。
Webサイト制作費(初期費用)
デザイン、ライティング、コーディング、サイト設定など、Webサイト制作の一連の業務にかかる費用です。必要であれば写真撮影や素材の購入なども発生します。決まりかった発注金額はなく、自作すれば0円で済むかもしれませんし、外部に依頼すれば何百万円かかることもあります。
サーバー費
オンライン上でWebサイトのデータを保管するために必要です。基本的にレンタルサーバーを利用し、継続的な支払いが必要です。よく使われるサーバーに、Xserverやlollipop!、さくらのレンタルサーバーがあります。
ドメイン費
「◯◯◯.com」のように独自のアドレスを取得するために必要です。初回の費用と継続的に支払いが必要な更新費があります。代表的なドメインに、.com、.net、.jpがあり、ドメインによって費用は異なります。
ツール費
CMSやノーコードツールなどのツールを利用する際に必要な費用です。継続的に支払いが必要で、サーバー費とドメイン費を含んでいることもあります。WordPressは有名なCMSで、無料で利用することができます。そのほかWiXやSTUDIOなど有料プランもあるノーコードツールもよく使われます。
Webサイト運営費
Webサイトの運営を他社に委託する際に必要な費用です。サーバー・ドメイン保守費や継続的なコンテンツ制作費などがあり、自分で更新を行えば料金はかかりません。サーバー・ドメイン保守管理は月に数千円〜数万円が一般的で、バージョン管理やデータのバックアップ、バグ修正といった内容です。
さいごに
僕はフリーランスのWebデザイナーとして、Webサイト制作全般のお仕事を中心に活動しています。
初めての方でもご安心してお任せいただけるよう、一つひとつ丁寧なやり取りを心がけています。ぜひお気軽にご相談ください。